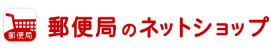お中元にお返しは必要?金額の相場とお礼状の文例、おすすめギフト

夏のギフトとして古くから定着しているお中元ですが、思いがけず相手からお中元をもらったときに、お返しはした方がよいのでしょうか。
今回は「お中元にお返しは必要かどうか?」というテーマについて、まとめました。
お礼状を書く際の文例や、お返しを贈る際の相場感についても紹介しています。
郵便局のネットショップで人気の「もらって嬉しいお中元ランキング」で上位に挙げられる情報をもとにしたおすすめギフトも掲載していますので、必見です。
お中元のお返しに関する基礎知識
お中元をいただいた際に、お返しは必要なのでしょうか。
お返しが必要かどうかを考える際には、まず「お中元を贈る意味」について知る必要があります。
●お中元にお返しは必要?
そもそも「お世話になっている」という「感謝の気持ち」を贈るものですので、お中元にお返しをする必要はありません。また、結婚祝いや出産祝いのようなお返しの風習といったものもありません。
しかし最近では同僚や友人、兄弟姉妹からのお中元も増え、同等の立場であることからお返しをするという方も増えてきています。
また、日本人特有の「いただき物にはお返しをする」という風習も相まって、同等の立場ではなくてもお返しをするという方が増えているようです。ネットなどでも「お中元の返礼品」とした商戦が繰り広げられています。
お歳暮も同じく、お返しをしないのが一般的です。贈り物をいただいた後に、お返しをしなくても問題はありません。
ただし、感謝の気持ちを伝えるために、お返しとは異なる形式で贈り物をするケースはあります。
●お返し以外の形式で贈り物をするには?
前項でお伝えした通り、お中元のお返しは不要ですが、何かしらの品物を贈りたい場合は、自分からお中元や残暑見舞い、残中見舞いを贈るようにするとよいでしょう。
目下の人から、付き合いのある取引先や上司など、目上の人に贈る際、お返しとして品を贈ると、マナー違反に捉えられるおそれがあるので注意が必要です。
地域によって、お中元のシーズンは異なります。
東日本は毎年7月1日から15日、西日本は7月15日から8月15日がメインシーズンになります。お中元のメインシーズンを過ぎる場合は、残暑見舞いとして贈るようにします。
贈る際には、熨斗(のし)紙の表書きを間違えないように注意しましょう。
関連記事:【お中元】暑中見舞いとして贈っても大丈夫?両者の違いを解説します
●贈り物の金額の相場は?
お中元をいただいた後に、自分から贈り物を贈る際には、まずお礼状を相手に送ります。
お礼状の送付が済んだら、改めて自分が贈る品物選びに入ります。
中身はまったく同じものを避け、できれば先方の好みのものを選びましょう。まだお中元の時期であれば贈答品として選ばれるもので大丈夫です。ただし金額に注意が必要です。お返しには、いただいたものの半額から同等額のものを選ぶのがマナーです。贈る相手が同等の立場であれば同等額のものを、立場の違う相手であれば半額から同等額より少し控えめな金額のものを選びましょう。
そして絶対に避けなければならないのが「いただいた金額以上の、明らかに高額な商品をお返しとして贈る」こと。これは「今後お中元は結構です」という意味にも捉えられます。嬉しかったから奮発してお返しをしよう!と高額なものを贈ってしまうとかえって失礼に当たり、大変不快な気分にさせてしまうので注意しましょう。
お返しの代わりにお中元を贈る場合、いただいた品物と同等または少し控えめな金額のプレゼントを用意するのがポイントです。高級フルーツや高価な銘柄のお酒など、明らかに値段が上回ってしまうような贈り物とならないように気をつけてください。
お礼状の書き方と文例
お中元をいただいたら、できるだけすぐにお礼の気持ちを伝えましょう。
この項目では、お礼の伝え方、お礼状の基本的な書き方について、例文を交えながら解説します。
●お礼状の基本的な書き方
お中元に限らず、何かいただき物をしたらお礼をするのがマナーです。
無事に届いたことを伝え、ありがとうの気持ちを伝えるようにしましょう。お中元の中身が生鮮食品の場合もあり、贈り手はやはり荷物が無事に届いているか心配になるものです。できるだけお礼は早くしておくべきです。
お中元が届いたら、まずは電話やメールでお礼の言葉を伝えましょう。最近ではメールでのあいさつも一般的になってきています。しかし、より丁寧にあいさつするべきお相手の場合は、きちんと電話であいさつをしておきます。
電話でのあいさつが難しい場合、取り急ぎのあいさつではなく、すぐにお礼状を書きます。もちろん電話やメールでお礼を伝えた場合も、その後にお礼状を送ります。
最近ではハガキをお礼状にすることもあるようですが、本来のマナーは縦書きの「手紙」を使います。こちらも届いたことがなるべく早く伝わるよう、当日または翌日には筆を取り、翌日から数日(2〜3日)中には投函できるよう、準備しましょう。
すぐに書けるように、お礼状用の手紙を常備しておくとよいでしょう。なお、親しい間柄であればこの「お礼状」を省くことも可能です。
お礼状の書き方にもマナーがあります。いくつか文例を紹介します。
●お礼状の文例
取引先に贈る場合
拝啓
○○の候、貴社におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、格別のご厚誼を賜りまして、心より御礼申し上げます。
さて、このたびは、お心尽くしのお中元の品をいただきまして、誠にありがとうございました。社員一同、暑さを忘れて美味しくいただきました。
これからますます暑さが本格化いたしますので、皆様におかれましては、どうぞご自愛下さいませ。まずは略儀ながら書中を持ちまして、御礼申し上げます。
敬具
謹啓
盛夏の候、貴社におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃は一方ならぬお力添えに預かり、心より深謝申し上げます。
さて、このたびは結構なお中元の品をご恵贈いただきまして、誠にありがとうございました。
◯◯◯のさわやかな清涼感が夏の暑さを忘れさせてくれるようで、スタッフ一同、大変喜んでおります。
暑さ厳しき折柄、皆様のご健康をお祈り致しております。
まずは書中をもってお礼申し上げます。
敬白
上司に贈る場合
拝啓
〇〇部長おかれましては、益々ご清祥のことと心よりお慶び申し上げます。
さて、本日は心のこもったお中元の品を頂戴しまして、誠にありがとうございます。
私の方が日頃お世話になっているところ、大変恐縮いたしております。
◯◯◯は家族みんなの大好物で、さっそく今晩にいただく予定です。
いつも細やかなお心遣いに、深く感謝しております。
暑さはまだまだ続くようですので、どうぞご自愛ください。
略儀ながら書中にて御礼申し上げます。
敬具
親戚に贈る場合
毎日暑さの厳しい日が続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
さて、このたびは思いがけず結構なお品をいただきまして、誠にありがとうございます。
ご丁寧なお心遣いを頂戴し、恐縮しております。
さっそく家族みんなでおいしくいただきました。
暑い日続きですが、体調を崩されませんようご自愛ください。
まずはお礼まで。
猛暑が続きますが、お元気でお過ごしでしょうか。
さて、このたびはご丁寧なお心づかいを頂き、本当にありがとうございました。
好物を覚えてくださっていて家族一同、喜んでおります。
この酷暑を元気で乗り切れますよう心よりお祈り申し上げます。
またお会いできる日を楽しみにしています。
お礼まで。
関連記事:法人のお中元、お礼状は何を書けばいい?
お中元のお返しとして贈る際に人気のギフト
お中元のお返しとして選びたいギフトをご紹介します。
いずれも、郵便局のネットショップで人気の「もらって嬉しいお中元ランキング」の上位に並ぶものばかりです。
※2022年度「郵便局のネットショップ」実績より
●お菓子の詰め合わせ
おしゃれな洋菓子・和菓子の詰め合わせはお中元として定番の、ギフトです。予算に合わせてさまざまな種類から選べるため、おすすめです。
焼き菓子やゼリーは日持ちしやすく、夏の時季に喜ばれやすい人気の贈答品です。
郵送の場合、アイスやジェラートなどを冷凍で贈るのも定番です。
●果物
夏に旬を迎えるスイカやメロン、マンゴーなどがおすすめです。
季節の果物を選ぶのが基本的なポイントで、ランキング上位にはたくさんのフルーツが並んでいます。桃やシャインマスカット、さくらんぼ、夏小夏なども大変人気の商品です。
果物の好き嫌いがわからない場合、フルーツジュースを選んでも良いでしょう。
ジュースは冷蔵保存で日持ちしやすく、子どもが多いご家庭でも喜ばれやすい傾向にあります。
また、果物を使ったスイーツも贈る相手を選ばず、喜ばれやすいです。
●グルメギフト
ハム、ソーセージをはじめとしたグルメギフトは、特別感があるために喜ばれます。冷凍して保存できるところも、好まれる理由のひとつです。
お中元として定番なのは、そうめんをはじめとした麺類です。夏バテの時期でも手軽に食べられるのが魅力です。
また、コーヒーなどの飲料も人気です。時期的にアイスコーヒーのセットなども好まれます。相手がコーヒー好きかどうかは、事前に確認して贈るようにしましょう。コーヒー以外の飲み物と詰め合わせになったドリンクセットも比較的人気です。
●カタログギフト
相手の好きなものがわからないときには、カタログギフトを贈るのもひとつの方法です。
幅広い種類の中から好みの商品を選べるため、ご家族と一緒に選ぶ楽しみもあります。
予算に合わせてチョイスできる上、実際の金額以上に豪華に見える商品が多数揃っているのが特徴です。
「お中元のお返し」は心をこめて
お伝えした通り、お中元には本来お返しをする習慣はなく、必ずお返ししなければならないという理由はありません。
ただ、先方からいただいたお中元に対しては、できるだけ早く「お礼の気持ち」をお伝えすることが大切です。
お中元をいただいた後に、自分から何かを贈りたいという場合には、本記事で紹介したギフト商品を参考に、選んでみてください。
今回掲載した商品は、いずれも「郵便局のネットショップ」に掲載されています。
豊富な種類が揃っており、きっと目的にあったギフトが見つかるはずですので、ぜひ探してしてみてください。
お中元の豆知識一覧
-
- お中元とは
- お世話になっている方々に感謝の気持ちを伝えるために、お中元の由来や歴史などをわかりやすくご紹介いたします。
-
- 暑中見舞いとして贈っても大丈夫?
- 一般的にお中元は品物、暑中見舞いはハガキというイメージがありますが、どちらも送るべきなのでしょうか。両者の違いやおすすめの品をご案内いたします。
-
- お中元とお歳暮の違い
- お中元を贈るとお歳暮も贈らないといけないのか気になりますよね。今回はお中元とお歳暮が両方必要か意味や違いをご紹介させていただきます。
-
- お中元のお返しはどうすればいい?
- お中元のようないただき物にお返しは必要なのでしょうか。一般的な「お中元のお返し」のマナーについてご紹介いたします。
-
- お中元のお礼状の書き方
- お中元のお礼状って何を書いていいのか分からないですよね。感謝の気持ちがしっかり伝わる書き方とマナーをご紹介させていただきます。
-
- 法人のお中元、お礼状は何を書けばいい?
- うっかり失敗してしまわないためにも、お礼状のポイントをご紹介いたします。
-
- お中元の選び方
- お世話になっているあの人に、お中元を贈ろうと思っても、いったい何を贈ればいいのでしょうか。お中元の選び方についてご紹介いたします。
-
- お子さんのいる家庭にお中元を贈るときの注意点
- 小さなお子さんのいる家庭の場合、アレルギー物質が含まれている可能性が高い食品や食材等を贈ってしまわないよう注意が必要です。
-
- 親戚にお中元を贈るときの基準
- 親戚にお中元を贈る際の基準や相場、品物は何が良い?といった疑問について解説いたします。
-
- お中元の定番そうめんの意味
- 実はそうめんには色々な意味や時代背景が込められています。その意味や、贈る理由をご紹介させていただきます。
-
- お中元に食べ物を贈ることが多いのはなぜ?
- お中元には食べ物を贈ることが多いですが、一体なぜなのでしょうか。今回はそんなお中元と食べ物に関する知識をご紹介します。
-
- お中元で嬉しいのはやっぱり実用品!
- お中元で何を贈るか迷う方に向けて、実用品の選び方を解説します。
-
- お中元に商品券を贈っても大丈夫?
- 目上の方に商品券を贈るのはマナー違反ではないかと心配する方も多いのではないでしょうか。その場合の注意点を解説します。
-
- お中元のご贈答マナー
- ご贈答マナーをご存知ですか?今回は恥をかかないご贈答マナーについてご紹介いたします。
-
- お中元は親同士も贈り合うべき?
- 両親が先方にお中元を贈る際のメリットやおすすめの品をご紹介いたします。
-
- 結婚後のお中元はどうするべき?
- 結婚するとお中元を贈らなければならない機会も増えるかと思います。結婚後のお中元について基本的な知識をご紹介いたします。
-
- 「喪中」だけどお中元を贈っても大丈夫…?
- 自分または相手が喪中の際のお中元のやり取りについてご紹介します。
-
- お中元のマナー
- お中元の基本的なマナーや、相手に合わせて知っておきたい注意点やルールをご紹介。
-
- ペットにだってお中元を贈る時代!
- 大切なペットと暮らすあの人に、今年はペット用のお中元を贈ってみませんか?
-
- お中元の渡し方・添える一言
- 今回は「手渡しするときの注意点」について紹介します。
-
- お中元の通販、利用しても問題ない?
- 正式なマナーとしてお中元を通販で贈る場合はどうしたらよいのかご紹介いたします。
-
- お中元を郵送するときのマナー
- 郵送のメリットを生かすマナーについてご案内いたします。
-
- もらって嬉しい人気お中元ランキング
- お中元の選び方に迷ってしまう皆さんに、「もらって嬉しい人気お中元ランキング」をご紹介いたします。
-
- お中元の時期はいつ?
- お中元の時期は地域によって異なります。お中元の受付開始時期や届ける時期の目安などを紹介いたします。
-
- お中元の熨斗のマナー
- 「のし」にはそもそもどんな意味があるのか、ご存知ですか?知っているようでよく知らない、「のし」についてご紹介いたします。
-
- お中元の適切な価格とは?
- いったいどれくらいの予算で贈り物を選べばいいのかわからない方も多いはず。お中元の適切な価格についてご紹介いたします。
-
- お中元の丁寧な断り方
- この記事では、お中元の断り方やマナー、注意点などについて詳しく解説します。
-
- お中元の挨拶|送り状・添え状の書き方
- この記事では、お中元の渡し方に適した挨拶の方法と手紙のマナーなどを紹介します。
-
- お中元に添える手紙の種類
- この記事ではお中元を贈るときや受け取ったときの手紙の種類や書き方、例文などを紹介します。
-
- お中元・夏ギフトおすすめ人気ランキング2026
- 2026年お中元ギフトの通販なら、郵便局のネットショップで。ギフト選びの参考に、予算、カテゴリ別など、おすすめのお中元ランキングを紹介します。
お中元の豆知識一覧
- お中元とは
- 暑中見舞いとして贈っても大丈夫?
- お中元とお歳暮の違い
- お中元のお返しはどうすればいい?
- お中元のお礼状の書き方
- 法人のお中元、お礼状は何を書けばいい?
- お中元の選び方
- お子さんのいる家庭にお中元を贈るときの注意点
- 親戚にお中元を贈るときの基準
- お中元の定番そうめんの意味
- お中元に食べ物を贈ることが多いのはなぜ?
- お中元で嬉しいのはやっぱり実用品!
- お中元に商品券を贈っても大丈夫?
- お中元のご贈答マナー
- お中元は親同士も贈り合うべき?
- 結婚後のお中元はどうするべき?
- 「喪中」だけどお中元を贈っても大丈夫…?
- お中元のマナー
- ペットにだってお中元を贈る時代!
- お中元の渡し方・添える一言
- お中元の通販、利用しても問題ない?
- お中元を郵送するときのマナー
- もらって嬉しい人気お中元ランキング
- お中元の時期はいつ?
- お中元の熨斗のマナー
- お中元の適切な価格とは?
- お中元の丁寧な断り方
- お中元の挨拶|送り状・添え状の書き方
- お中元に添える手紙の種類は?
- お中元・夏ギフトおすすめ人気ランキング2026