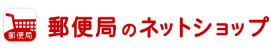お中元の熨斗(のし)のマナー|水引の種類と結び方、正しい表書き

お中元をはじめ、贈答品に使用される包装紙のことを「熨斗(のし)紙」と呼びます。
今回は「熨斗(のし)」の由来や、「熨斗紙」の違い、「水引(みずひき)」とはどのようなものかなど、熨斗に関する基本的な知識を解説します。
表書きの書き方など、お中元を贈る際に押さえておくべきマナーについても解説しています。状況や贈る相手によっては失礼に当たることもありますので、「これからお中元を贈りたい」という方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
お中元の熨斗(のし)に関する基礎知識
まずは「熨斗(のし)」について、見ていきましょう。熨斗とはいったい何なのでしょうか?
その由来についても、説明いたします。
●熨斗(のし)とは?
「熨斗(のし)」と聞いて、なにを思い浮かべますか?よく贈答品を買ったときに「熨斗はどうされますか?」「お願いします」といったやり取りの後、店員さんが贈り物を包んでくれる、あの紙を思い浮かべる方も多いはず。実はこれ、「熨斗(のし)紙」であって「熨斗」そのものではないのです。
「熨斗」とは、「熨斗紙」の右上にある飾りのようなもののことを指します。金封などにも付いているのをご存じの方も多いでしょう。もともとは「伸(の)しあわび」が由来で、祝賀の贈答の際に、贈り物に添えられていた伸しあわびが簡略化されたものです。
「伸しあわび」とはあわびを薄く切り伸ばし、生干しにして木槌で叩き伸ばし、さらに天日干しにして乾燥させたもの。四方を海に囲まれた日本では、古来より神事のお供え物として用いられていました。伸して乾燥させたあわびは栄養価が高く保存もきくことから、中世では武士の出陣の際祝儀に用いられ、戦場での貴重な保存食にもなりました。
それがのちに「長生き」「長持ち」の印として重宝がられ、次第に慶事の儀式に高価な贈答品として用いられるようになり、時代の移り変わりとともに和紙に包んだ伸しあわびを「熨斗(のし)」として贈答品に添えられるようになりました。
熨斗紙は、簡略化された熨斗と水引を印刷した包装紙のことです。結婚の内祝いや出産祝いなどのお祝い事に用いられるほか、お中元をはじめ、お歳暮や暑中見舞い、残暑見舞いを贈る際にもよく使われています。
関連記事:お中元とは?由来やお歳暮との違い、マナーについて一挙に紹介!
●「外熨斗」と「内熨斗」の違い
熨斗(のし)紙の掛け方は、「外熨斗(のし)」と「内熨斗(のし)」の2種類に大別されます。
贈り物の包装紙の上から熨斗(のし)紙を掛けることを外熨斗(のし)と言います。手渡しするときや、感謝やお祝いの気持ちを表したいときには外熨斗がおすすめです。
化粧箱の上に熨斗紙をかけ、さらに上から別の包装紙で包むことを内熨斗(のし)と言います。内側が傷つきにくいため、郵送でお中元を贈る場合や、内祝いのときには内熨斗がおすすめです。
お中元の熨斗(のし)に適した水引の種類
次は「水引(みずひき)」について、基本的な知識を解説します。
水引にはいくつかの種類があり、贈る状況によって使い分ける必要があります。
●水引の種類と結び方
「熨斗(のし)紙」に、熨斗と共に印刷されている結び目のデザインが「水引」です。熨斗だけでなく、こちらもあわせて覚えておくことをおすすめします。
お中元の「熨斗紙」としては、すでに紅白5本の花結びタイプ(蝶結びと表現される場合もあります)の水引が印刷されている場合がほとんどです。花結びタイプは「何度でもほどけて結び直しができる」ことから、婚礼以外の一般的な祝い事(出産、入学など)に使用します。
ちなみに婚礼に関しては、お祝い事ではあるけれど繰り返しを嫌うため、固く結ばれてほどけない縁起の良い結び方の「結び切り」タイプの水引を使用します。
それ以外に、結び切りでも弔事の白黒の水引、簡単にはほどけないけれど互いの輪が交じっていていつまでも良い付き合いができるという意味から「アワビ結び」のタイプの水引、法事用の白と黄色の水引など、いくつか種類があります。
包んだ和紙を結びとめるための「水引」の名称は、和紙をよって紙縒り状にし、水糊を引いて乾かし固めたことからきています。
原形である白は、神聖・清浄を意味しています。「熨斗」と一緒に覚えておくようにしましょう。
●水引の本数
水引の本数は、縁起が良いとされる5本あるいは7本が適しています。お祝い事では、2つに割り切れてしまう偶数は縁起が悪いと考えられることから、割り切れない数字である「奇数」を選ぶ必要があるためです。
本数は5本が基本となり、簡略的にする場合は3本、丁寧にする場合は7本にすることがあります。
例外として10本の水引を結ぶこともありますが、これは「5本を二重にした結び方」で、両家が手をしっかりと結び合うというような意味合いがあり、婚礼や弔事で用いられます。お中元の場合の本数は5本が基本で、丁寧に贈る場合は7本を使用します。
また、水引の色は、めでたい席で使用される紅白を選びます。
贈る相手や自身が喪中の場合、熨斗や水引がないものを選ばなければいけません。
お中元の熨斗(のし)紙の正しい書き方とマナー
「熨斗(のし)紙」には、正式な書き方があります。
個人で贈る場合、連名で贈る場合でそれぞれ異なりますので、間違った書き方をしないように注意が必要です。
●熨斗(のし)紙の正しい書き方
熨斗紙には、お中元の表書きを行います。表書きとは、慶事や弔事の際に熨斗紙の上部に書く文言、つまり贈り物に関する項目のことです。
「お中元」や「お歳暮」以外にも、「御祝」「寿」「卒業御祝」といった文言のほか、弔事では「御仏前」「御霊前」といった項目を書きます。
お中元では表書きのほか、水引の下部には名入れ(贈る人の名前)を行う必要があります。
表書きと名前は、濃い墨の毛筆や、筆ペンを使って丁寧に書きます。また、横書きではなく必ず縦書きで書くのがポイントです。
ボールペンや鉛筆、黒以外のペンを使って書いてはいけませんので、注意してください。
-
- 個人で贈る場合
- お中元の場合、水引の上の方に「お中元」または、「御中元」と書くようにします。
水引の真下には、中央に贈り主のフルネームを記載します。会社名を入れる場合には、名前の右上に少し小さく書きましょう。
英数字は、読みやすいカタカナ表記にするのがおすすめです。
-
- 連名で贈る場合
- 3名以下の連名で贈る際には、名前は役職・立場が高い順に右から書きます。
4人以上の場合、代表者の名前を書いて左に「他一同」と記載するか、「○○部一同」など、団体名でまとめて書くようにします。この場合、一人ひとりの名前は、贈り物の中包みに書くようにしましょう。
●短冊熨斗(のし)に関するマナー
きちんと「熨斗紙」をかけ、表書きをして丁寧に贈っても、実は失礼に当たることがあるのをご存じでしょうか。
そもそも熨斗紙とは、「熨斗」を付け「水引」を引く作業を紙に直接印刷してしまうことで、手間と時間を省いたもの。いわば現代用に効率化を求めて簡略化されたもので、百貨店やショッピングモール、ネット通販などでよく使用されています。
正しいマナーでお贈りするべき状況で、簡易的な熨斗紙をかけてお贈りすると失礼に当たります。
正統なマナーでお渡ししたいときには簡略化された「熨斗紙」は使用せず、必要な場合はきちんと「熨斗」を付け「水引」を引くように注意してください。
また、熨斗紙と同じ役割を持つ「短冊熨斗(のし)」もあります。
短冊熨斗とは、近年用いられる機会が増えた簡易的な熨斗紙のことです。「環境への配慮」という観点から、エコにつながるコンパクトな短冊熨斗が選ばれる機会が少しずつ増えています。
短冊熨斗も熨斗紙同様の簡易的なものですので、伝統を重んじる方や、目上の方への贈り物の際には失礼に当たる場合があります。贈る際には注意しましょう。
関連記事:お中元のマナー|基礎知識からギフトの選び方や贈り方を紹介
●外熨斗と内熨斗の違い
熨斗には、包装紙の上に掛ける「外熨斗」、化粧箱に掛けてから包装する「内熨斗」の2種類があります。
相手先まで直接伺い、手渡しする場合には外熨斗を選ぶようにしましょう。表書きを見えるようにしておくことで、贈る目的や感謝などの気持ちをしっかりと伝えられるためです。
お中元以外には、結婚・出産祝いなども外熨斗が望ましいと言われています。
外熨斗に対して、内熨斗はお中元を郵送する場合に適しています。配送中に熨斗紙に傷がつかないようにすることが理由です。
相手や自身が喪中の場合は、熨斗と水引のない熨斗紙を選ぶ必要があります。
●できれば送り状を先に郵送する
お中元を手渡しではなく配送する場合、送り状を事前に送っておくのが正式なマナーであるとされています。
先に送り状を送っておくことで、直接先方に伺うことができない場合でも丁寧な気持ちを伝えることができます。
送り状はメールではなく、手紙で送付することが望ましいとされています。友人など、親しい相手の場合は電話やメールで済ませることもありますが、ビジネス関係などのフォーマルな付き合いの相手には、手紙で送った方が良いでしょう。
表書きのように毛筆や筆ペンを使う必要はありませんが、できればボールペンや鉛筆ではなく、万年筆やサインペンを使って手書きにするようにしましょう。
お中元に欠かせない熨斗(のし)
今回は、お中元の熨斗について、詳しく解説しました。
慶事の際に使用されるというだけで、本当は知らなかった熨斗や熨斗紙のこと。
ひも解いてみれば、昔からの伝統が現代風にアレンジされ、いまも息づいていることがうかがえます。お中元だけでなく、今後あらゆる場面で必要となってくる熨斗について、これを機にぜひ覚えておきましょう。
お中元を贈る際には、印刷された熨斗紙を使用することが一般的です。
「郵便局のネットショップ」なら、指定した期日までに熨斗紙の付いたお中元を届けることができます。
「お中元・夏ギフト特集2026」には、豊富な種類の商品が盛りだくさん。きっと目的にあったギフトが見つかるはずです。
お中元の豆知識一覧
-
- お中元とは
- お世話になっている方々に感謝の気持ちを伝えるために、お中元の由来や歴史などをわかりやすくご紹介いたします。
-
- 暑中見舞いとして贈っても大丈夫?
- 一般的にお中元は品物、暑中見舞いはハガキというイメージがありますが、どちらも送るべきなのでしょうか。両者の違いやおすすめの品をご案内いたします。
-
- お中元とお歳暮の違い
- お中元を贈るとお歳暮も贈らないといけないのか気になりますよね。今回はお中元とお歳暮が両方必要か意味や違いをご紹介させていただきます。
-
- お中元のお返しはどうすればいい?
- お中元のようないただき物にお返しは必要なのでしょうか。一般的な「お中元のお返し」のマナーについてご紹介いたします。
-
- お中元のお礼状の書き方
- お中元のお礼状って何を書いていいのか分からないですよね。感謝の気持ちがしっかり伝わる書き方とマナーをご紹介させていただきます。
-
- 法人のお中元、お礼状は何を書けばいい?
- うっかり失敗してしまわないためにも、お礼状のポイントをご紹介いたします。
-
- お中元の選び方
- お世話になっているあの人に、お中元を贈ろうと思っても、いったい何を贈ればいいのでしょうか。お中元の選び方についてご紹介いたします。
-
- お子さんのいる家庭にお中元を贈るときの注意点
- 小さなお子さんのいる家庭の場合、アレルギー物質が含まれている可能性が高い食品や食材等を贈ってしまわないよう注意が必要です。
-
- 親戚にお中元を贈るときの基準
- 親戚にお中元を贈る際の基準や相場、品物は何が良い?といった疑問について解説いたします。
-
- お中元の定番そうめんの意味
- 実はそうめんには色々な意味や時代背景が込められています。その意味や、贈る理由をご紹介させていただきます。
-
- お中元に食べ物を贈ることが多いのはなぜ?
- お中元には食べ物を贈ることが多いですが、一体なぜなのでしょうか。今回はそんなお中元と食べ物に関する知識をご紹介します。
-
- お中元で嬉しいのはやっぱり実用品!
- お中元で何を贈るか迷う方に向けて、実用品の選び方を解説します。
-
- お中元に商品券を贈っても大丈夫?
- 目上の方に商品券を贈るのはマナー違反ではないかと心配する方も多いのではないでしょうか。その場合の注意点を解説します。
-
- お中元のご贈答マナー
- ご贈答マナーをご存知ですか?今回は恥をかかないご贈答マナーについてご紹介いたします。
-
- お中元は親同士も贈り合うべき?
- 両親が先方にお中元を贈る際のメリットやおすすめの品をご紹介いたします。
-
- 結婚後のお中元はどうするべき?
- 結婚するとお中元を贈らなければならない機会も増えるかと思います。結婚後のお中元について基本的な知識をご紹介いたします。
-
- 「喪中」だけどお中元を贈っても大丈夫…?
- 自分または相手が喪中の際のお中元のやり取りについてご紹介します。
-
- お中元のマナー
- お中元の基本的なマナーや、相手に合わせて知っておきたい注意点やルールをご紹介。
-
- ペットにだってお中元を贈る時代!
- 大切なペットと暮らすあの人に、今年はペット用のお中元を贈ってみませんか?
-
- お中元の渡し方・添える一言
- 今回は「手渡しするときの注意点」について紹介します。
-
- お中元の通販、利用しても問題ない?
- 正式なマナーとしてお中元を通販で贈る場合はどうしたらよいのかご紹介いたします。
-
- お中元を郵送するときのマナー
- 郵送のメリットを生かすマナーについてご案内いたします。
-
- もらって嬉しい人気お中元ランキング
- お中元の選び方に迷ってしまう皆さんに、「もらって嬉しい人気お中元ランキング」をご紹介いたします。
-
- お中元の時期はいつ?
- お中元の時期は地域によって異なります。お中元の受付開始時期や届ける時期の目安などを紹介いたします。
-
- お中元の熨斗のマナー
- 「のし」にはそもそもどんな意味があるのか、ご存知ですか?知っているようでよく知らない、「のし」についてご紹介いたします。
-
- お中元の適切な価格とは?
- いったいどれくらいの予算で贈り物を選べばいいのかわからない方も多いはず。お中元の適切な価格についてご紹介いたします。
-
- お中元の丁寧な断り方
- この記事では、お中元の断り方やマナー、注意点などについて詳しく解説します。
-
- お中元の挨拶|送り状・添え状の書き方
- この記事では、お中元の渡し方に適した挨拶の方法と手紙のマナーなどを紹介します。
-
- お中元に添える手紙の種類
- この記事ではお中元を贈るときや受け取ったときの手紙の種類や書き方、例文などを紹介します。
-
- お中元・夏ギフトおすすめ人気ランキング2026
- 2026年お中元ギフトの通販なら、郵便局のネットショップで。ギフト選びの参考に、予算、カテゴリ別など、おすすめのお中元ランキングを紹介します。
お中元の豆知識一覧
- お中元とは
- 暑中見舞いとして贈っても大丈夫?
- お中元とお歳暮の違い
- お中元のお返しはどうすればいい?
- お中元のお礼状の書き方
- 法人のお中元、お礼状は何を書けばいい?
- お中元の選び方
- お子さんのいる家庭にお中元を贈るときの注意点
- 親戚にお中元を贈るときの基準
- お中元の定番そうめんの意味
- お中元に食べ物を贈ることが多いのはなぜ?
- お中元で嬉しいのはやっぱり実用品!
- お中元に商品券を贈っても大丈夫?
- お中元のご贈答マナー
- お中元は親同士も贈り合うべき?
- 結婚後のお中元はどうするべき?
- 「喪中」だけどお中元を贈っても大丈夫…?
- お中元のマナー
- ペットにだってお中元を贈る時代!
- お中元の渡し方・添える一言
- お中元の通販、利用しても問題ない?
- お中元を郵送するときのマナー
- もらって嬉しい人気お中元ランキング
- お中元の時期はいつ?
- お中元の熨斗のマナー
- お中元の適切な価格とは?
- お中元の丁寧な断り方
- お中元の挨拶|送り状・添え状の書き方
- お中元に添える手紙の種類は?
- お中元・夏ギフトおすすめ人気ランキング2026